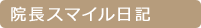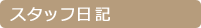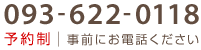あいうべ体操の効果
- Home >
- お知らせ
ガム効果!!
顎を動かしてガムを噛むと・・・
①唾液を分泌を促進して、唾液による自浄作用もあり、
むし歯や歯周病の予防につながります。
②脳への血流がアップして、脳の発達、認知予防につながります。
③唾液は消化を助け、胃腸の働きを活発にします。
④口の周りの筋肉をよく使うかとで、顎の発達をたすけ、
顔立ちもよくなります。
⑤唾液に含まれるペルオキシターゼという酵素が
食品の発がん性を抑えガン予防につながります。
スマイル歯科で販売しています。
リカルデントボトル¥1100 ポスカ¥800

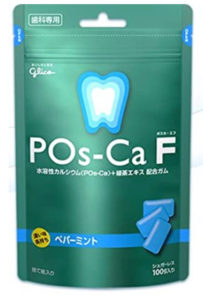
NAKANOSAKURA
高齢者に多い誤嚥
食べ物や唾液を飲み込む際、口から食道へと送られるが、誤って気管に入り込んでしまうのが「誤嚥」である。高齢になるとうまく飲み込めない嚥下障害が起こりやすく、誤嚥を生じるリスクが高まる。
通常は誤嚥しそうになると嚥下反射が働き、むせてせきをすることで気管から異物を吐き出す。しかし、加齢とともに飲み込む機能や嚥下反射が低下すると、高齢者ではうまく吐き出せない場合がある。
さらに、口の中には肺炎を引き起こす細菌を含むさまざまな細菌がすみついており、歯磨きが不十分で不潔な状態が作られると増殖する。「誤嚥によって肺炎の病原菌を多く含んだ食べ物や唾液が気管に入り、気管から肺に侵入して炎症を起こします。これが誤嚥性肺炎である」

誤嚥性肺炎
① 虫歯・歯周病の予防
歯と歯の間・歯の付け根部分や、歯と歯ぐきの境目に歯垢が溜まると虫歯や歯周病を引き起こします。口腔ケアでむし歯や歯周病予防の期待ができます。
②誤嚥性肺炎の予防
日本人の死亡原因の3位である肺炎、特にご高齢者に多い誤嚥性肺炎は、唾液や飲み物、食べ物が誤って気管から肺に入り込んでしまう誤嚥の際に口腔内の細菌が肺に入ってしまうことで起きます。
口腔ケアで口腔内細菌数を減らし、飲み込みの機能を維持向上することで誤嚥性肺炎を発生率を下げる効果が期待できます。
③唾液の分泌を促す
要介護の方の多くが口の機能が低下し、内服薬の副作用などにより唾液が出にくくなり口腔内が乾燥しがちです。また唾液が口の中をきれいに保つ自浄作用も低下しています。
口腔ケアでお口の中を刺激することで唾液が出やすくなります。
④ 口臭の改善

虫歯や歯周病が進行している場合や、舌の表面に汚れが付着すると(舌苔)口臭の原因になります。
口腔ケアを行い、歯と歯茎の境目や舌、頬などを優しく擦り口の中を清潔に保つことは口臭を予防できます。
仲野 桜
歯間ブラシ効果
食べものが詰りやすい歯と歯の間は、ハブラシの毛先が届きにくく、歯周病の原因となるプラーク(歯垢)が残りやすい場所です。歯みがきだけでは取りきれないプラークも歯間ブラシを使うことで効果的に取り除くことが出来ます。

歯間ブラシのサイズについて
| サイズ※ | 最小通過径※ | 適応部位 |
|---|---|---|
| SSS | 〜0.8mm |
 前歯など歯と歯の隙間が特に狭いところ |
| SS | 0.8〜1.0mm | |
| S | 1.0〜1.2mm |
 軽度の歯茎の退縮部位や歯並びの悪いところ |
| M | 1.2〜1.5mm |
 歯茎の退縮部位やブリッジ装着の周辺など |
ブラッシングの効果
歯と歯ぐきのブラッシング

●ブラッシングの目的
ブラッシングの目的は、歯を磨くことだけではありません。
たとえ歯が1本もなくなったとしても、歯ぐきのマッサージのために、ブラッシングを続けることが大切です。
1.口の中にたまった食べかすや歯垢を取り除き、細菌の繁殖を抑えて歯石を防ぐ。
2.歯ぐきを歯ブラシでマッサージして、血行をよくする。
●ブラッシングのコツ
毎日ブラッシングしているのに、歯石やむし歯などのお口のトラブルが減らない場合は、磨いているつもりでもきちんと磨けていないのかもしれません。
歯ブラシを横に動かして、ごしごしと磨いているだけでは汚れが落ちきらないうえ、歯がすり減ってしまうこともあります。
ブラッシングのコツをつかんで、正しい方法で効果的に磨きましょう。
NAKANO SAKURA
8月の旬の食べ物『ピーマン』『トマト』
「ピーマン」 ピーマンの旬は6~8月です。ビタミンA、C、カロテン、ポリフェノール(クエルシトリン)など豊富な栄養が含まれています。ピーマンは緑色と思っている方がほとんどですが、実は、緑色のピーマンは未熟な状態で、完熟すると赤や黄色、だいだい色になります。
美味しく新鮮なピーマンの見分け方は、肉厚でつやがある物がよいです。乾燥に弱いので、新聞紙やビニール袋に入れて野菜室で保存してください。
そして驚くことに、ピーマンとパプリカの違いを断定できる定義はないのです。同じナス科のトウガラシ種であり、実の厚みや味で区別しています。イメージとしての種分けは、「ピーマンは緑で小ぶり」「パプリカは肉厚で大きい」ですね。
「トマト」 トマトの旬は6~8月頃です。美味しいトマトの見分け方は、丸みがあって重さもある物です。完熟したトマトはビニール袋に入れて野菜室へ、まだ硬く青いトマトは熟すまで常温保存が向いています。
ビニールハウスで1年中栽培していますが、昔は日本の気候が合わず栽培が難しかったようです。今では高温多湿の日本に適した品種に改良されています。
とは言っても本来トマトは高温多湿が苦手な野菜ですので、春~初夏のトマトの方が、糖度も栄養価も高くなります。
nakano sakura
夏バテを予防するにはどんな食事を取ればいい?
夏は、のどごしのよいそうめんや冷麺などを食べる機会が多く、炭水化物に偏った食事になりがちです。
夏バテ予防のためには、不足しやすいタンパク質やビタミン、ミネラルなどを意識して取る必要があります。
肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質が多い食材と、ビタミンやミネラルを含む野菜も毎食取り入れましょう。
ビタミンの中でも特に注目して取りたい栄養素はビタミンB群。
中でも、食事で取った糖質を代謝し、エネルギーに変えてくれるビタミンB1は、疲労回復に欠かせない栄養素です。
ビタミンB1が豊富な食材には、ウナギや豚肉などがあります。ビタミンB1の吸収を促進する「アリシン」という成分を含む、ニラやネギと一緒に食べると良いでしょう。
ビタミンB1は、体に留めておくことができないという特徴があるため、こまめに取ることも大切です。
ビタミンB1に限らず、栄養価の高い旬の野菜も積極的に取りましょう。
トマト、エダマメ、モロヘイヤ、ゴーヤ、パプリカなどの旬の夏野菜は、ビタミンやミネラルが豊富。彩りも良く、目からも食事を楽しむことができます。
また、食欲増進効果の期待できる、香辛料や香味野菜を取り入れるのもおすすめです。
カレー粉やニンニク、コショウ、ワサビ、ネギ、シソの葉、ミョウガ、ショウガなどをうまく活用することでおはしが進むメニューに。レモンなどの柑橘系やお酢も食欲増進に役立ちます。
消化吸収を助ける「ムチン」という成分を含む、オクラやナガイモなどのネバネバ食材も積極的に取り入れると良いでしょう。
Nakano Sakura
紫陽花の花言葉
●アジサイの見た目からついた花言葉
アジサイには、両性花と装飾花の2種類の花があります。
小さな花が密集している中央の花が両性花で、周囲を囲っている花が装飾花です。
両性花の集まりが、家族の結びつきを表しているように見えるため、「一家団らん」や「仲良し」という、母の日にぴったりな花言葉もあります。
なお一見して花びらのように見える部分の装飾花ですが、これは萼(がく)が変化したものであり、正確に言うと花ではないのだそうです。
●色ごとの花言葉
アジサイにはほかにも、花の色ごとに違った花言葉があります。
例えば青のアジサイは「辛抱強い愛情」、白は「寛容」、ピンクは「元気な女性」という花言葉がつけられているのです。
アジサイを母の日に贈る際、色で迷ってしまったら、花言葉から選んでもいいかもしれません。
参考にしてみてください。
NAKANO SAKURA
歯ブラシの交換時期について
歯を清潔に美しく保つために欠かせない歯磨き。でも歯ブラシの交換時期に悩んでいる方は意外と多いのではないでしょうか。
「まだ使える」と思っていても交換時期が過ぎているかもしれません。そこで歯ブラシの交換時期の目安を簡単にご紹介致します。
歯磨きは「朝だけ」「夜だけ」という方もいるかも知れませんが、「毎食後磨く」という人が一番多いのではないでしょうか。毎食後、1日3回歯磨きをした場合、歯ブラシの寿命は約1か月と言われています。
「2~3か月は使っていた」という方はこれから1か月ごとに交換してみましょう。汚れの取れ具合が変わるかもしれません。
しかし、たとえ1か月未満でも、歯ブラシは毛先が広がったら寿命といわれています。すぼまった毛先だからこそ歯の汚れや歯垢を書き落とすことができます。毛先が広がれば、弾力性も汚れをかきだす能力も落ちます。
なので毛先が広がった歯ブラシでいくら丁寧にブラッシングをしても歯はきれいになりません。
あまり早く歯ブラシの毛先が広がってしまうという場合は、力を入れてブラッシングし過ぎているという場合があります。適度な力でソフトにブラッシングするよう心がけてみましょう。
替えたハブラシは年末の大掃除等に使ってみてはいかがでしょうか。
nakano SAKURA
あいうべ体操の効果
- アレルギー性疾患(アトピー、喘息、花粉症、鼻炎)
- 膠原病(関節リウマチ、エリテマトーデス、筋炎、シェーグレン)
- うつ病、うつ状態、パニック障害、全身倦怠
- 腸疾患(胃炎、大腸炎、便秘、痔)
- 歯科口腔(歯周病、ドライマウス、顎関節症、虫歯)
- その他(イビキ、尋常性乾癬、高血圧、腎臓病、風邪など)

NAKANO SAKURA
スタッフ日記
最新の投稿
- 2024/09/06
- 10月休診のお知らせ
- 2022/04/23
- 5月休診日のお知らせ
- 2021/11/22
- 12月休診日のおしらせ
月別アーカイブ
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (6)
- 2025年9月 (11)
- 2025年8月 (10)
- 2025年7月 (8)
- 2025年6月 (11)
- 2025年5月 (7)
- 2025年4月 (10)
- 2025年3月 (6)
- 2025年2月 (6)
- 2025年1月 (14)
- 2024年12月 (13)
- 2024年11月 (11)
- 2024年10月 (9)
- 2024年9月 (12)
- 2024年8月 (10)
- 2024年7月 (14)
- 2024年6月 (10)
- 2024年5月 (12)
- 2024年4月 (9)
- 2024年3月 (8)
- 2024年2月 (14)
- 2024年1月 (8)
- 2023年12月 (11)
- 2023年11月 (12)
- 2023年10月 (9)
- 2023年9月 (11)
- 2023年8月 (6)
- 2023年7月 (10)
- 2023年6月 (12)
- 2023年5月 (11)
- 2023年4月 (10)
- 2023年3月 (14)
- 2023年2月 (8)
- 2023年1月 (15)
- 2022年12月 (10)
- 2022年11月 (11)
- 2022年10月 (13)
- 2022年9月 (11)
- 2022年8月 (12)
- 2022年7月 (14)
- 2022年6月 (14)
- 2022年5月 (12)
- 2022年4月 (16)
- 2022年3月 (11)
- 2022年2月 (14)
- 2022年1月 (13)
- 2021年12月 (15)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (10)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (11)
- 2021年7月 (11)
- 2021年6月 (13)
- 2021年5月 (13)
- 2021年4月 (11)
- 2021年3月 (12)
- 2021年2月 (12)
- 2021年1月 (14)
- 2020年12月 (9)
- 2020年11月 (13)
- 2020年10月 (11)
- 2020年9月 (12)
- 2020年8月 (11)
- 2020年7月 (12)
- 2020年6月 (13)
- 2020年5月 (11)
- 2020年4月 (17)
- 2020年3月 (8)
- 2020年2月 (13)
- 2020年1月 (14)
- 2019年12月 (12)
- 2019年11月 (10)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (8)
- 2019年8月 (11)
- 2019年7月 (13)
- 2019年6月 (10)
- 2019年5月 (11)
- 2019年4月 (13)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (16)
- 2019年1月 (11)
- 2018年12月 (14)
- 2018年11月 (15)
- 2018年10月 (15)
- 2018年9月 (15)
- 2018年8月 (15)
- 2018年7月 (16)
- 2018年6月 (16)
- 2018年5月 (15)
- 2018年4月 (15)
- 2018年3月 (17)
- 2018年2月 (11)
- 2018年1月 (14)
- 2017年12月 (10)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (6)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (6)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (5)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (8)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (5)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (8)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (8)
- 2014年7月 (4)
- 1225年1月 (1)
CONSULTATION HOURS